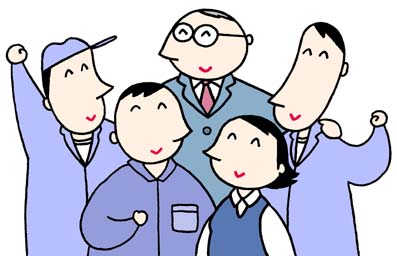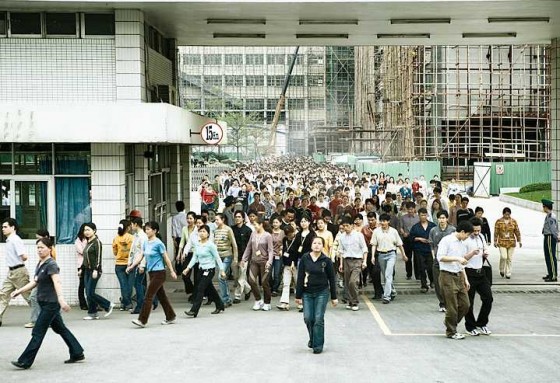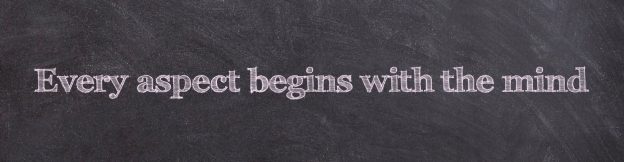先週のニュースで、国内ががんばり続けている靴下メーカが「滑らない靴下」を受験生マーケットに投入した話を、ご紹介した。
滑り止め機能付きの靴下を受験生に売ると言うアイディアはすばらしいが、市場規模が小さすぎる懸念がある。そこで、日本国内でがんばっている靴下メーカを応援するために、滑らない靴下を拡販するための新たな市場創造のアイディアを読者様に求めた。
二名様からアイディアをいただいた。ご紹介したい。
※上海のN様のアイディア
いつもメールマガジン楽しみ読ませてもらっています。
今回の「滑らない靴下」を継続的に購入して頂ける方法を考えてみました。
なかなか参加できないですが、東莞和僑会メンバーなので投稿します!
- 「すべらない靴下」のポイントは「使用者」と「購買者」が分かれている事がポイントだと思います。
受験生がすべらない靴下を買うと考えると購買機会が限られてしまいます。しかし、両親、祖父母、親戚、友人が「ギフト」として贈ると考えると購買機会はぐっと増えます。特に高齢者に訴求できるように、老人ホームや老人会カラオケサークルや俳句会など高齢者が集まりやすいサークルに絞ってチラシやDMをすれば、販路は広がると思いました。- 靴下全体で継続購入してもらえる付加価値として、最近私は1枚900円の靴下を買った経験があります。ユニクロで買えば三足1000円で買えるこのご時世に1枚900円で買ったのは、ロッククライミングシューズ専用の靴下です。
素足のように薄く、それでいて縫い目が少なく、汗の吸収性、抗菌性が高い靴下です。ロッククライミング自体は日本ではマイナースポーツですが、世界にはたくさんのプレーヤーがいます。クライミングシューズで有名な企業とタイアップして販売すれば、世界的に自社販売網を持っていなくても、販売しやすいかもしれません。頭の体操として、こんな方法を考えてみました。
※深センのN様のアイディア
こんにちは。
部外者ですが、宿題をもらいました(笑)
・・・・無料で楽しい話題をいつももらってる引け目もあって(爆)靴下、くつした、さて自分は靴下をどういう視点で見ているか。
- 足先と踵の部分が擦り減ってきたらそろそろ何か買うかな。
- スーツだろうがなんだろうが、オヤジ臭い靴下はイヤだ。
- 柄は女子にモテル系orウケル系、つまり自分では選ばない。嫁や娘に選ばせる。
- 夏場は若者風の短いの、冬場は暖かめの。
- 足が臭い、加齢臭が気になる年頃(笑)
こんなことを考えてみると、『女子が選ぶ、お父さん、お兄ちゃん、弟に、息子に履いてもらいたい靴下』 がキーワードかな。
炭効果で臭い防止みたいな靴下を見たことありましたが、デザインがまったくいけてない。
今回の事例、滑らないということは相手側、つまり靴のインナーへの影響はどうなのだろうか。滑らないということはインナーへの負担が心配。
一方女性陣ではどうだろうか、
男性にもてたい靴下選び、とは思わないだろう。
いかにかわいいか、履き心地がいいか、安っぽい生地はいやだ、そんなところだろうか。
ユニクロのヒートテック靴下・・・・、優れているのにかわいいデザインが揃えられていない。今回の宿題は 『継続的に購入していただける付加価値』 だ、かわいいだけでは長続きしまい。
やはり機能美を追求したい。
- 保温性に優れ
- 生地は薄くても長持ち
- 相手側の靴の種類を選ばない
- 加齢臭を抑制できる
- お客様のデザイン提案に対応できる(デザインオーダーメード)
・・・・過日のシルシルミシルで今は靴下裁縫は自動機なのでデータがあればデザイン対応できると見ている
そんな企画を提案します。
ソーシャルモノ造り分科会のメンバーは,必ず宿題提出などと書いたので誤解をさせてしまったかもしれない(笑)私は、このメールマガジンの読者様全員を、仲間だと思っている。
たかが靴下、それをどうすれば売れるか考える。
良い頭の体操になったのではないかと思う。
お二人に共通している「靴下は使用者本人が買うのではない」と言う指摘は、なるほどと関心した。何度か靴下を自分で購入したことがあるが、出張中・単身赴任のため、やむを得ず自分で購入した。普段は家内が買って来る。と言う事は男性用靴下を選択しているのは、女性が大半を占めていると考えた方が良いかもしれない。
私の場合、衣類もほとんど女性陣が選んでいる。家内、娘だけではない、母親も含まれる。推定年齢88歳の母親でさえ、未だに「かわいい」は重要らしい。靴下にも、女性目線の「かわいい」を入れる事は重要かもしれない。
靴下のデザインは女性がした方が良い。と言うのが結論になろうか(笑)
デザインに関しては「個」への対応がキーワードになると思っている。世界に一つしかない靴下だ。IT技術と、生産の電脳化が出来れば、意外と簡単だろう。
もう一つのお二人の共通点は「機能」だろう。
スポーツへの応用は、クライミングだけではなかろう。ランナーも靴の中が蒸れる対策を必要としている。私は蒸れるのを通り越し、汗で濡れてしまう。これを解決すれば、ランナー市場が手に入る。
これを解決出来れば、受験生市場よりは大きな市場となろう。しかもリピートが期待出来る。受験生市場では、リピートは考え難い。幼稚園のお受験を入れたとしても生涯5回しかない。しかも途中で失敗すれば、残りのリピートはない。受験生の合格不合格は企業にとって神頼みであり、企業が努力しても改善出来る話ではない。
保温に着目すれば、スノボー、スキーにも使える。昔はウールの厚手の靴下を着用したモノだが、最近はブーツのインナーが改善されており、薄手の靴下の方がフィット感は良い。
スポーツへの応用を検討する、と言うのが二番目の結論か。
靴下が滑って困ると言う経験をした事がないが、運動能力が低下している老人には良い機能かもしれない。デイケアセンター、老人ホーム等館内はスリッパ着用となっている所も多い。スリッパを止めて、滑らない靴下着用とする。と言うアイディアを思いついた。
最後の結論は、お年寄り御用達。
大変面白い議論が出来たと思う。こんな所から実ビジネスのアイディアに発展すれば、もっと面白いが、少なくとも頭の体操が出来た。頭も筋肉も、使えば使うほど鍛えられる。またこんな企画を考えてみたい。
このコラムは、2013年10月14日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第331号に掲載した記事を修正・加筆しました。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】