以前「答えのない質問」というタイトルの雑感を書いた。
答えがない質問の例として「フェルミ推定」と「父母未生のお前は何処にいた」という禅問答をご紹介した。
今回は小学校の教室で行われた設問をご紹介したい。
「虹はなぜ七色か?」
この質問には答えがある。
虹は太陽光が大気中の水滴に反射して発生する。
太陽光には全ての波長の光が含まれている(全ての色が含まれている)。
波長の異なる光は屈折率が異なる。
という原理を理解していれば、虹が七色である事を説明可能だ。
しかし、小学低学年の子供達はこの原理を理解していない。その子供達になぜ虹は七色か問い、クラスで議論させるそうだ。
同様に「桜の花は咲く前にどこにあったか?」という設問を与え議論させる。
この授業では、教師は何も教えず議論を聞いているだけ。
この教師の狙いは分からないが、「教える→覚える」という伝統的な教育方法にない効果がある事は容易に想像がつく。
この授業で物理現象や植物に関して興味を持った子供は、図書館に行き調べるかも知れない。自分で答えを求めて調べた事は、容易には忘れない。
自分で調べなかった子供も、後に物理の授業を受けた際に小学校の時の授業を思い出し膝を打って納得するだろう。「腑に落ちた」状態となれば、記憶に定着する。
この様な指導法は学校教育だけではなく、社会人に対する教育にも有効だと思う。企業内で行われる研修や、部下の指導で答えを教えない指導をする。
全てを、答えを教えない方法で指導にする事は、不可能かも知れない。教えてしまった方が手っ取り早い。
しかし、
教えずに考えさせる。考える過程で学ぶ。
教えずに失敗させる。その失敗から学ぶ。
こういう指導法の効果は高そうだ。
命取りにならない失敗をたくさん部下に経験させる事が出来るのが、優秀なリーダの条件かも知れない。
このコラムは、2016年10月3日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第496号に掲載した記事です。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月・水・金曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】

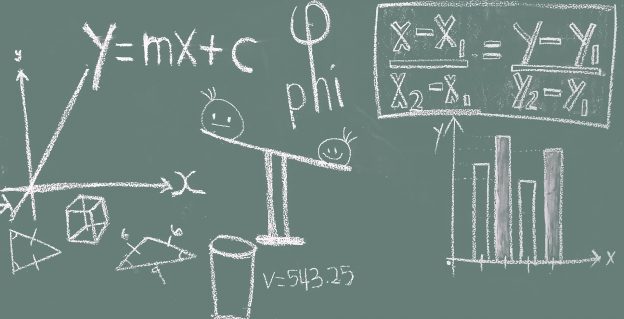





 私と同じ様な年頃の皆さんは、小学生の頃、二宮金次郎が薪を背負い本を読んでいる銅像や石像が、学校に有ったのを覚えておられると思う。我々は二宮金次郎と覚えているが、大久保忠真から二宮尊徳と言う名を貰っている。「徳を尊ぶ」五常(仁義礼智信)を説き「推譲」を実践した二宮尊徳にぴったりの名前だ。
私と同じ様な年頃の皆さんは、小学生の頃、二宮金次郎が薪を背負い本を読んでいる銅像や石像が、学校に有ったのを覚えておられると思う。我々は二宮金次郎と覚えているが、大久保忠真から二宮尊徳と言う名を貰っている。「徳を尊ぶ」五常(仁義礼智信)を説き「推譲」を実践した二宮尊徳にぴったりの名前だ。