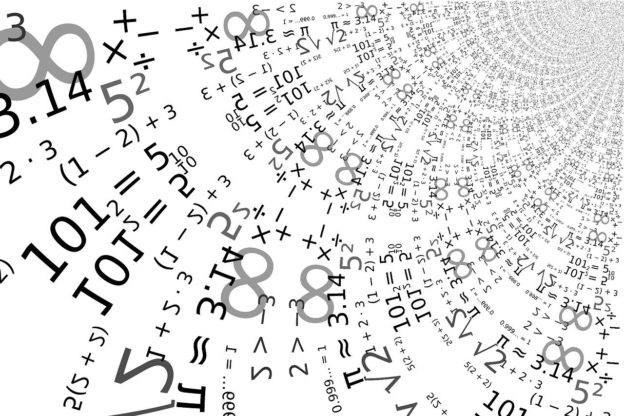以前中国企業に5Sの指導をしていて、奇妙な要求を受けたことがある。
工場内をレイアウトに合わせ、床に色を塗りたいと言う。一般的に作業エリアは緑、通路はオレンジ色に塗る事が多い。テープの色などと合わせて教えるが、通路に足跡も表示したいと要求を受けた。歩行方向を指定したいのならば、矢印で十分だが、やはり足跡を表示したいという(笑)
事情を聞き出すと、中国ローカルのコンサル会社に5Sをやるならば、通路に足跡を表示して、従業員がそれに従って歩く様にするのが良いとすすめられたそうだ。
床の色を塗り分けると、レイアウト変更の度に床を塗り直さなければならない。
そのため床の色は一色にして区画表示のテープで通路と作業エリアを表示する。
この方がムダなコストがかからないはずだ。
作業エリアや、部品の一時置き場などに表示するカンバンも簡単に入れ替えが出来る様にする。
足跡を表示する事に反対はしないが、ムダなコストをかけずに、フレキシブルにやる方が良い、と説得するが、経営者はどうしても足跡を表示したい様だ。
くだんのローカル系コンサル会社は、床の色塗りから足跡の表示までセットで請け負ってくれるそうだ。こんな事をしただけで5Sが良くなるとは思えない。元々内装工事業者が、工場の塗装仕事を請け負いたくてコンサルをしているのではと、勘ぐりたくなる(笑)
5Sの整頓を一言で言えば「見える化」だが、このコンサル会社は、5Sをやっている事を見える化してくれる様だ。
お金をかけてでも5Sを一生懸命やろうという決意は買うが、見栄えだけを狙うのでは長続きはしない。
通路をきちんと表示することにより、安全性が高まる、ムダな動きが少なくなる、現場にムダなモノが置けなくなる、などの具体的効果を狙うべきだ。
わざわざ足跡をいくつも表示する事はないだろう。
どうしても足跡を表示したいのであれば、足跡の間隔を90cmにして、テキパキと歩く様にしてはどうか、と提案した(笑)
このコラムは、2013年1月28日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第294号に掲載した記事です。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】