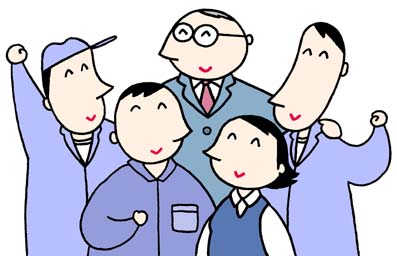今度ばかりはさすがにヤバイ。
世界一の自動車メーカ、超優良企業のトヨタといえど、今トヨタは存続の危機に直面している。1950年労働争議により直面した経営危機以来の大ピンチだ。
世間では、一連のリコール問題の深層を探り、問題の真因を捉えようとする動きが活発になっている。
今回目にしたコラムは、部品の共通化とリコール問題について検討している。『「大型リコールの原因は部品共通化」のウソ、真因は製品の品質検証体制』では、筆者の日野氏は部品共通化擁護の立場でコラムを書いている。
トヨタは、設計効率の向上、生産効率の向上のために部品の共通化を強力に推し進めて来た。今回のリコール問題の拡大は「部品の共通化」にありとする一部の議論に対し、日野氏は「部品の共通化」は表層の問題点であり、真の問題点は「部品の共通化を品質保証できていない点にある」と評論している。
私流に言わせてもらえば、品質保証が出来ていない部品の共通化などありえない。ただ同じ部品を使いまわしているだけである。部品の共通化というのは、適用できる設計要件を明確にした上で、その品質を保証できるということだ。共通化は、設計の標準化、部品の標準化のプロセスを経て達成される。
元々部品・モジュールは特定の動作環境の下で設計され、検証・評価されている。それをそのまま共通化部品として取り扱うわけには行かない。当然動作環境の変動により、見えていなかった問題点が顕在化することがありうる。
部品・モジュールの機能に着目してブラックボックス化してしまうと、大きな過ちを犯す。動作環境、製造環境などの設計要件を明確にしておき、共通部品を選択する設計手順を標準化しなければならない。
この様な過程を経て、部品の共通化は設計ミスの排除、設計効率の向上、生産効率の向上、在庫量の削減、コストダウンに貢献することが出来る。
しかし極度の共通化は、設計の自由度を奪う。
また共通化をするということは、進歩をいったん停止するということである。
車を嗜好品として考えたとき、部品の共通化はデザインの自由度を奪うことになる。車は単なる移動手段ではない。所有する喜び、運転する喜びをユーザに与えるべきものだ。
元々トヨタはそのような車造りが下手だ。レクサスからトヨタの名前を排除しているのもその現われだろう。
トヨタよりはホンダ、Panasonicよりは(昔の)Sonyの製品の方が、ワクワクするのは私だけではないだろう。
インドや中国メーカによる車の価格破壊に付き合う必要はない。
消費者の価値観に対しきちんとコストをかけるモノ造りをすれば、高くても売れるはずだ。
トヨタは量の追求で大きくなった。一定の量を生産していないと利益が出ない構えを作ってしまった。残念ながら、低価格車にも対応してゆかなければならない体質が出来てしまっている。
車が単なる移動手段であったときは、安い車を市場投入すれば右肩上がりに売り上げも利益も伸びる。しかしそのような市場で利益を上げ続けるのは困難だ。コストダウンに明け暮れ疲弊する。そしてある日金属疲労が限界点に達したように、ポキッと折れてしまう。品質不良による損失は、直接利益の部分をマイナスする。それをカバーするための売り上げは10倍以上は必要だろう。
日本の時計メーカは、高品質・高機能な時計を大量に生産し、同時に貧乏も量産してしまった。その間スイスの高級時計メーカは、顧客の価値観にしっかりコストをかけ、高級品を少量だけ作り生き残っている。
日本はこの様なモノ造りがうまくできていない。
大量同一規格製品の市場は中国にくれてやり、魅力的品質製品のモノ造りに転換してゆかなければならないだろう。
このコラムは、第143号2010年3月8日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第143号に掲載した記事です。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】