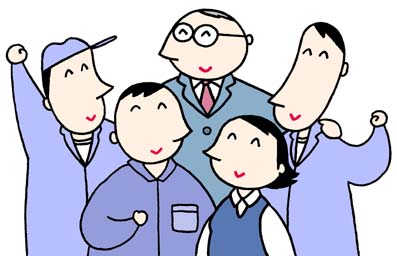未来をイメージして今の仕事の方向性を決める。
こんなことを言うと反論の声が聞こえてきそうだ。
「去年の今頃、この不景気を予測できただろうか?今の時代は予測不可能の時代だ。予測不可能ならば、その場その場で 臨機応変に対応する力をつけるのが先決だ。」
もっともな意見だが、10年後どうありたいかというイメージなしで事業が経営できるだろうか?
日本が戦後すばらしい発展を遂げたのは、欧米の先進企業があったからだ。
彼らを手本としていれば、そのまま未来をイメージすることになった。
ありたい姿が実在するのだからこんなに簡単なことはない。
しかし今はトップを走らなければならない状況となっている。
未来は自分の中にしかないのだ。
10年後は今より更に予測不可能な時代になっているはずだ。
顧客の要求は更にワガママになっており、マーケットの変化も読めなくなっている。そういう時代に対応できる経営者を育てているだろうか。
10年前の延長で今を経営できていれば、同じモノを大量に作ればよい業務遂行型のマネージャがいれば十分だろう。
今必要なのは業務革新型のマネージャだろう。
今の業務をうまくこなすマネージャではなく、今の業務を破壊し業務を革新できるマネージャだ。
ほんの少し前、EMSが脚光を浴びていた。しかしEMS生産・OEM生産では利益を生み出す付加価値の創造が難しい。委託元からのコストダウン要求に辟易しながらビジネスをしても楽しくはない。
10年後とは言わずも5年後の自分達のありたい姿を具体的なイメージとして描き、そのために必要な人財と技術の仕込みを今していなければならない。それが経営者の仕事だと思う。
このコラムは、2009年3月9日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第88号に掲載した記事です。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月・水・金曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】