「使っているコメを分けてくれませんか」
シンガポールの名門ホテル、シャングリラに店を構える懐石料理店「なだ万」の料理長、石塚隆也(42)は客からよくこんな注文を受ける。なだ万が同国や香港で使うのは農機メーカー、クボタから仕入れたコメだ。
(以下略)
全文
(日本経済新聞電子版より)
海外に住んでいると、日本米の美味さが身にしみて分かる。
この記事によると、精米した後にコンテナに積載して輸出するので、日本米と言えど味は劣化する。赤道直下のシンガポールでは、コンテナ内の温度は60℃を超える。
クボタはこれを解決するために、シンガポールに精米所を設け、日本から玄米でコンテナ輸送をしている。
中国では、日本米の輸入規制が有る。以前試しに少量日本米を輸入した際は、国内産の数倍の単価でも、飛ぶ様に売れた。中国に輸入する米は、中国検疫当局が認定した精米所で精米しなければならない。現在日本国内には一カ所しかなく、認可の申請を出しても、検疫官が来てくれないそうだ。
クボタと同じ方法を採用すれば、中国国内で精米出来、味の劣化だけではなく、非関税障壁も突破出来そうな気がする。
何事も諦めなければ、突破口が見つかるモノだ。
「神子原米」と言う能登羽咋市のブランド米が有る。これも諦めなかった一人の市役所職員が作り上げたブランド米だ。
故郷の羽咋市で住職をする高野誠鮮氏は、市役所の臨時職員として仕事をしていた。そして「限界集落」神子原村の活性化プロジェクトを担当する。「限界集落」と言うのは人口の半数以上が65歳を超える集落をさす。いわば、放っておけば近いうちに消滅してしまう、絶滅危惧村落と言う意味だ。当時、村で最年少の人は50歳だったと言う。このまま行けば、新しく子供が生まれる可能性は、ほぼゼロだ。
まず村の経済基盤を確立しようとした。当時は一戸当りの平均収入は年間90万円にも満たない状態だった。村の生産物と言えば米しかない。棚田で栽培される米はコシヒカリであり、天然のわき水がある、一日の寒暖の差が大きい事などにより、味は評判だ。しかし農協経由で出荷する米は「石川米」として扱われる。農協に出荷せずにブランド米として販売しようと農家に説得するが、賛同者はわずか3戸。全体で5、60戸ある農家の95%からは賛同が得られなかった。
ちゃんと売れる様になったら、皆で会社を興してブランド米として販売する事を約束して、高野氏自身がマーケティングをした。
神子原米をブランディングするために、誰かに食べてもらおうと考えた。「神子原米」にこじつけて米国大統領(当時はブッシュ)とローマ法王に手紙を書いた。ブッシュからは何の返事もなかったが、バチカン市国大使館から電話が来た。ローマ法王に神子原米を献上することができた。
これが有名になり、2年目はあっという間に完売となる。
売り切れ後も、問い合わせの電話が鳴り止まない。東京から電話をして来たと言う女性に「既に売り切れですが、東京の有名デパートならばまだ在庫が有るかも知れません」と高野氏は答える。そして数日後東京のデパートから、神子原米を取り扱わせてくれと電話が入る。高野氏のマーケティングマジックで、どんどん販路が広がって行った。
その後酒も造ろうと考え、外国人が、日本酒に対する感想をブログなどに書き込んでいるのを、ネットで集め分析する。「ワインのような」「フルーティ」と言うキーワドに着目し、日本酒をワイン酵母で作ってしまう。能登は杜氏が多くいて、ワイン酵母で清酒を作るなんて到底認められるモノではなかろうが、それをチャレンジしてしまう。
高野氏は、国内での販売促進のために、ローマ法王や欧米人の酒に対するイメージを使った。「マーケットに聞け」と良く言うが、国内マーケットに販売するために、世界のブランドを作ろうとしたのが、高野氏の戦略だったと推測している。
中小企業にブランドを作る資金などない、と諦めてはいけない。
高野氏の手元に有ったのは、羽咋市の地域振興予算60万円だけだ。高野氏には自らのアイディアと情熱以外に使える物はなかったはずだ。
ただ、高野氏はこのプロジェクトを担当する際に上司への稟議はしない、事後報告を市長にすればよい、と言う約束を取り付けている。事なかれ主義の同僚、上司に足を引っ張られないポジションを予め確保した。
金はなくとも、情熱とアイディアがあれば何とかなる。
そして革新に着いて来れない旧守派に足をとられない仕掛けを用意しておく。こんな所が、不可能を可能にするコツだろうか。
高野誠鮮著
「ローマ法王に米を食べさせた男」
このコラムは、2014年10月20日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第394号に掲載した記事に加筆しました。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月・水・金曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】

-624x208.jpg)
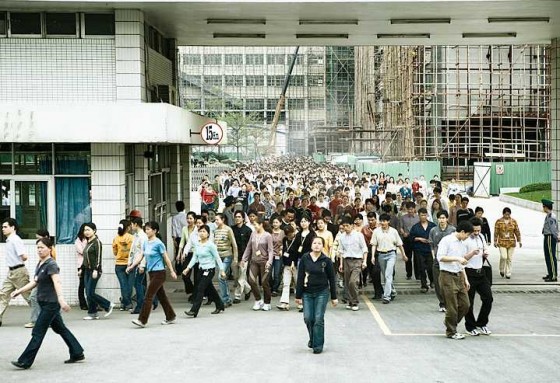

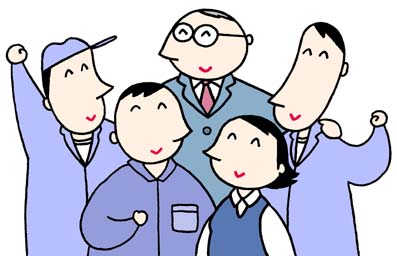


-624x312.jpg)
