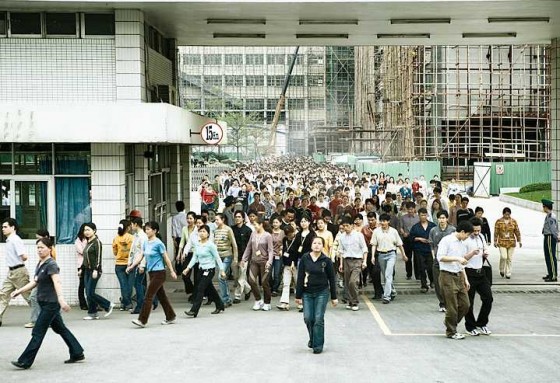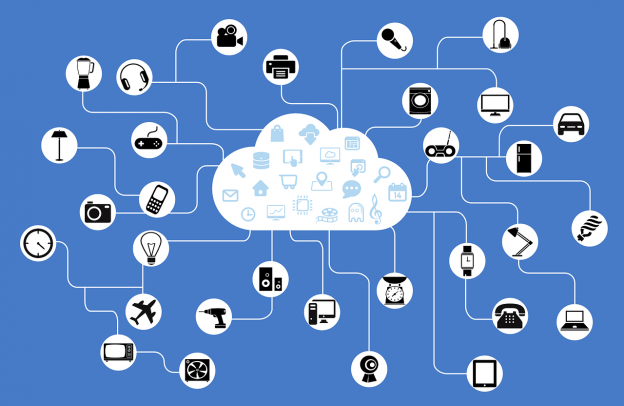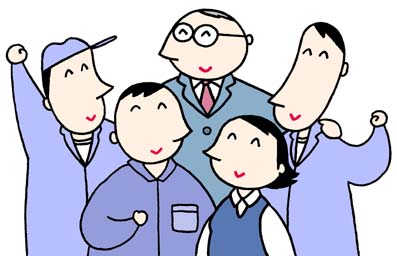先週インターネットのニュースを閲覧していて「製品評価技術基盤機構」(Nite)という独立行政法人を発見した.ホームページでは製品安全・事故情報を公開している.「安心を未来につなぐナイトです」というキャッチフレーズだ.過去の事故事例から未来に発生するかもしれない不具合・事故を未然に防ごうという趣旨である.
是非このサイトを時々ご覧になって,自社製品の不具合・事故の未然防止に役立てていただきたい↓
「製品評価技術基盤機構(Nite)」
今日はこのサイトにあった事故ファイルから事例を紹介したい.
【事故通知内容】
CDプレイヤーを使用していたところ、電源アダプターから煙が出た。
【事故原因】
電源回路の平滑用コンデンサー製造時に混入した異物がセパレーターに損傷を与え、電極間にスパークが発生し発熱したため内圧が高くなり、防爆弁が作動して内部の電解液が蒸気となって噴出したものと推定される。
【再発防止措置】
コンデンサーメーカーにおいて、作業者の教育訓練を強化し、作業現場の温度管理を強化して環境の安定化を図るとともに、工程ごとの部品管理の改善を図っている。
アルミ電解コンデンサの不良事故である.
残念ながら事故原因の追及が甘い.コンデンサーに異物が混入した原因までさかのぼる必要がある.
どんな異物であったのかが特定できれば,どの工程で混入したのかが分かるはずだ.
例えばアルミ箔のくずが混入していたのならば,アルミ箔を一定の幅に切りそろえる工程でバリが発生していた事が考えられる.
非導電性の異物であれば,アルミ箔と絶縁紙を巻き取る工程で混入したと考えられる.
このように発生工程と原因を更に特定をしなければ,正しい対策は打てない.
したがって再発防止措置のところに「作業者の教育訓練」がトップに出てきたりする.もちろん作業者に対する教育訓練は必要だがこれだけでは不十分だ.
真の原因に対する対策が不足している.
例えばアルミ箔のバリが混入していたのならば,バリが発生しないようにする.
箔の巻き取り工程で異物が混入したのならば,異物が発生しないようにする.
皆さんの工場では再発防止対策に,
「従業員に注意をした」とか
「従業員に再教育をした」
などという言葉が並んでいないだろうか?
このコラムは、2008年9月15日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第51号に掲載した記事です。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月・水・金曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】