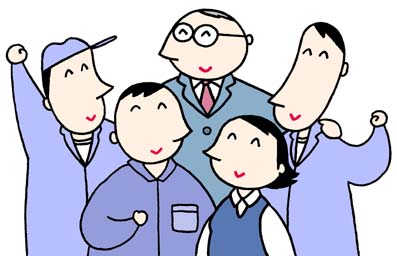先週の経営相談室では、社内研修に関するご相談をご紹介した。
その後思い立って、『「やる気を出せ!」は言ってはいけない』を読み直した。
この本は行動科学の石田淳氏の著作で、部下育成について書かれた本だ。
『「やる気を出せ!」は言ってはいけない』石田淳(著)
石田淳氏とは以前香港でお目にかかったことがあり、以来何冊か著作を読ませていただいた。
「部下のモチベーションを上げたい」と言うリーダの願いは、どんな業種でも共通のモノだろう。しかしモチベーションとか、やる気と言うのは人の内側にあるモノであり、外から見ることができない。つまり色々な工夫を凝らし、部下のモチベーションを上げようとしても、その成果は計測不可能だ。
この様な状況では、努力の結果が目に見えず、改善すべき点も見つからない。
石田氏のマネジメント手法は、モチベーションが上がっているときの行動に焦点を当て、その行動が自発的に発生する回数をモチベーションの代用特性とする。これでモチベーションが計測可能となり、何をすればモチベーションが上がり、何をすればモチベーションが下がるかが分かる。
いわゆる計測とフィードバックによる改善のループが出来る訳だ。
彼の書籍の中に、好ましい行動が継続出来ない理由に関する記述がある。
このメルマガ読者様の参考になると思い、ご紹介したい。
継続することにより、好ましい結果が得られる行動は強化したい。
例えば、禁煙とかダイエット。仕事で言えばコツコツと毎日積み上げる様な作業だ。
これらの作業行動は、何度も積み上げる事に意味がある。しばしばおろそかになり継続する事が難しい。目標に対して行動が不足してしまうので「不足行動」と言う。
一方、過剰に発生する行動により、本来期待した行動が出来なくなってしまう行動を「過剰行動」と言う。ダイエット中に間食をする。仕事中にムダな休憩をしばしば取る。こういう行動が「過剰行動」に当たる。
好ましい結果を達成するためには、過剰行動を減らす必要がある。
従って目標を達成するためには、不足行動を増やし、過剰行動を減らせば良い。
モチベーションとかやる気と言う不可視のモノではなく、目に見える行動で評価出来ることになる。
しかし評価出来る様になっても、なぜ好ましい行動が不足し、なぜ好ましくない行動が過剰になるのかを知らなければ、改善出来ない。
不足行動は通常長期間の行動の積み上げで成果が見える。
禁煙やダイエットは一日で達成出来るモノではない。長い間継続して初めて効果が現れる。
一方過剰行動の方は、すぐに成果が得られる。
イライラしている時に1本煙草吸えばすぐに、好ましい精神状態になる。空腹の時に間食をすれば、満腹感と言う成果がすぐに手に入る。
つまり、
不足行動により成果が現れる時期>過剰行動により成果が現れる時期
もしくは
不足行動による短期メリット<過剰行動による短期メリット
と言う不等式が成立し、不足行動を起こさずに過剰行動を起こすことになる。
不足行動を起こす動機付けには「恐怖」もあり得る。
例えば、明日までにこの仕事をやらなければクビになる、と言う状況になれば必死になって仕事をするだろう。
医者に煙草をやめなければ明日死ぬと言われればすぐに禁煙出来るだろう。
しかし恐怖による動機付けが有効になる事は余りない。有効になったとしても効果は短期的だ。
ではどうすれば、不足行動を継続することができるのか?
上記の不等式が成り立たなくすれば良いのだ。
不足行動により得られる短期メリットを付加してやる。
又は過剰行動により得られる短期メリットを小さくしてしまう。
こういう工夫ならば出来ると思うがいかがだろうか?
このコラムは、2013年11月18日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第336号に掲載した記事に加筆しました。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月・水・金曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】