 臨済宗円覚寺・横田南嶺管長のお話をうかがう機会があった。もちろん直接お目にかかってお話を伺ったわけではない。ありがたい事に、世界中のどこにいても、日本の高僧のお話を聞く事が出来る。IT技術により、私たちは計り知れない自由を手に入れている。
臨済宗円覚寺・横田南嶺管長のお話をうかがう機会があった。もちろん直接お目にかかってお話を伺ったわけではない。ありがたい事に、世界中のどこにいても、日本の高僧のお話を聞く事が出来る。IT技術により、私たちは計り知れない自由を手に入れている。
もちろん横田老師や私が若い頃は、そのような自由はなかった。(驚く事に横田老師は私より相当お若い様だ)横田老師は、若い頃に影響を受けた書籍の著者や、尊敬する方に直接手紙を書き会いに行っている。直接会って話を聞く。ネット上にある情報から得られる知識の数十倍、数百倍の価値があるはずだ。
既に若くはない私も、見習わなければならない。
横田老師のお話で特に印象に残ったのは「戒」に関するお話だ。「戒律」「十戒」などの「戒」だ。「受戒」「戒名」は、私の様な葬式の時だけ仏教徒になる様な不信心な者でも知っている。
「戒」とはやってはいけない戒律と言うイメージが有った。
しかし横田老師によると、「戒」とは良き習慣、良き習慣に導くと言う意味だ。
つまり「殺すべからず」と言う戒律は、やってはいけない事として、殺人罪と言う罰則とセットで、守らされている。
「戒」を良き習慣と理解すれば、「殺すべからず」と言う戒律は「命を愛する」と言う良き習慣となる。
良き習慣が、正しい智慧を生む。正しい智慧に基づく行いが慈悲である。
お釈迦様は、良き習慣を身につける事により幸せになる方法を説かれたのだ。
ここまで聞いて、すとんと腑に落ちた。
これは5Sの「躾」そのものだ。私には仏教を説き、布教する力はないが、5Sを通して、「戒」を説く事は出来る。
5Sとは、働く人々を幸せにするモノでなくてはならない。その結果企業の利益が上がる。これが5Sの根本原理・原則でなければならない。
「いろはにほへと―鎌倉円覚寺 横田南嶺管長 ある日の法話より」
このコラムは、2016年7月4日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第483号に掲載した記事です。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月・水・金曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】



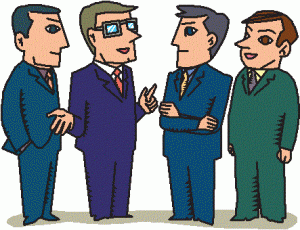 リーダーの資質として「予知能力」をあげたい.
リーダーの資質として「予知能力」をあげたい.