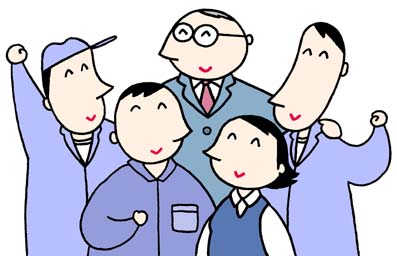宇宙に行くと体重が減る──。宇宙航空研究開発機構の松本暁子医長らのグループが、30~50歳代の宇宙飛行士延べ514人について、宇宙へ行く前後の体重変化のデータを集め、そんな解析結果をまとめた。
調査対象は、1961年から2004年の間に宇宙へ行った米国、日本、カナダ、欧州、ロシアの飛行士のうち、米航空宇宙局(NASA)の記録があった男性延べ434人、女性同80人。宇宙飛行の前後で体重が平均2.13%減っていた。
宇宙では、無重力のため筋肉量が減るほか、体液の移動など様々な要因で、体重減少が起きるらしい。地球に帰還し3カ月~1年経った後も、飛行前に比べて平均約1%軽かった。
(asahi.conより)
こういうデータの出し方は,大変胡散臭い.
例えば私の場合体重68kgなので,2.13%の体重増減といえば,約1.4kgだ.このくらいの体重変動ならば,朝食前と夕食後では十分起こりうる.また2,3kmジョギングしただけでも,その程度の体重は減る.
たまたまあったデータで,科学的な結論を導こうというのが間違いだ.
宇宙に行く前後の体重データには,測定時条件の誤差+測定誤差+宇宙効果が含まれている.測定時条件とは,測定時に空腹だったかどうかなどの身体的な条件による誤差.測定誤差は,測定器具と測定方法による誤差.これらの誤差が,宇宙効果よりも小さくなくては有意とはいえない.
しかも宇宙効果の中には,個人差によるバラツキ,宇宙滞在期間によるバラツキが含まれる.
従ってこの調査によって得られるのは,宇宙に行くことにより「筋肉量の減少」と「体液の移動」によって体重が減少するかもしれないという仮説だけだ.
体重減少のメカニズムを考えると「筋肉量の減少」は,再評価する価値がありそうだ.しかし「体液の移動」に関しては,移動しても体液はまだ体内にあり,体重変動があるとは思えない.
科学的な結論を得ようとするならば,検証可能な仮説を立て,正しいデータにより検証をしなければならない.
当然データには誤差によるバラツキ,効果によるバラツキが含まれる.これは統計的に検証可能だが,正しいデータを取らなければ誤差によるバラツキの方が大きくなってしまい,有意な結論を導くことはできない.
まずは具体的な仮説を設定する.
この例で言えば「宇宙に行く前後で体重減少がある」は,まだ具体的ではない.
「宇宙滞在時に筋肉量が減り体重が減る」という仮設にすれば,具体性が増す.
その仮説に基づき,必要なデータを集める.
この例ならば,宇宙滞在期間と体重減少量との間に相関があるかどうかという仮説を検証するデータを集めればよい.
その上で各個人の体重減少量のバラツキが,誤差によるバラツキより十分大きいことが検証できれば,この仮説は有意であると結論をつけることができる.
今「イシューからはじめよ」という本を読んでいる.
著者の安宅和人氏は,脳神経科学の研究者であり,経営コンサルタントのキャリアを持つという変わった人だ.
本書の中で,問題を解くことを考えるのではなく,まず問題を見極めよ.その上で価値のある結果を導け.と説いている.
今まで問題解決に関する書籍にはたくさん出会ってきたが,安宅氏のようにまず問題を見極めよ,という主張は新鮮であり,もっともだと思う.
ご興味がある方は是非一読をお勧めする.
ただし今回のコラムに書いたような統計的手法について語っている本ではない.
このコラムは、2011年7月11日に配信したメールマガジン【中国生産現場から品質改善・経営革新】第213号に掲載した記事を修正・加筆しました。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】は毎週月・水・金曜日に配信している無料メールマガジンです。ご興味がおありの方はこちら↓から配信登録出来ます。
【中国生産現場から品質改善・経営革新】